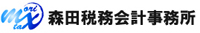武富士贈与税判決にみる、還付加算金への誤解と矛盾
武富士の元会長から長男が受けた株の贈与をめぐる課税問題で、最高裁は18日、
国の追徴課税処分を取り消した。国の逆転敗訴である。
長男は既に延滞税等を含め1,585億円を納付しており、予想される400億円の還付加算金を含め、約2,000億円が還付されることとなる。
本稿では、この「400億円の還付加算金」を対象とする。
なおこの判決そのものについては、別に「当然の武富士贈与税裁判全面敗訴に、無反省の国税」をタイトルとするコラムに記載したので、詳細はそちらをご覧いただきたい。
さて読売新聞は、還付加算金を次のように説明している。「誤った課税で取りすぎた分を納税者に返還する際に加算される利子。(中略)利率は延滞税と同じで、近年は4%台。現在の普通預金の金利約0.02%を大幅に上回っている」。
この説明自体には誤りはない。しかしこの記載は、普通預金の利率に比べる等、「いかにも払い過ぎで、武富士の長男は儲けすぎているのではないか」といった発想が透けてみえてくる。
さらには記事には次のような記載もある。不況で税収が減少する中、約400億円もの”利子”を支払う結果となり、国税当局には落胆が広がると同時に、納税者の(還付への)反発を危惧する声も上がった」。
しかし還付加算金には二つの意味がある。
ひとつは利息としての側面。ただしそれに納税が強制された金額を使用することができなくなったことに対する賠償や補填が加わっていると思われる。つまり、それを有利に運用するなり、事業に投入するなりの機会を、行政が強制的に奪ったのである。であればこの程度の利率とするのは当然といえよう。つまり、これを普通預金の利息と比較すること自体がおかしい。
ふたつ目として、これは当局の不当な課税への抑制策としての意味を持つ(以下この狙いを「抑制への重し」という)。
それは納税者が脱税や滞納した際に課される、利息としての延滞税(脱税等には、別途罰としての加算税が課される)との対比で考えれば分かる。つまり両者の利率は公平となるように同率と定められている。当局の不当な課税と納税者の脱税を戒める意味(「抑制への重し」)を込めているのである。
ところが本来は同じはずの還付加算金と延滞税には、不公平というべき大きな違いがある。それはそれぞれが発生した場合における両者への課税方法の違いである。
まず還付加算金。これを受け取った側には、これを雑所得としてその額に所得税と住民税が課税される。すなわち今回の400億円には、実質的に両税の合計の50%の税が課され、手取りは200億円となる。この点、400億円をまるまる手にすることができるかのような報道は、誤りといわなければならない。
その一方、延滞税は様子が異なる。一般に業務に関連して金利を支払えば、それは支払利息といった必要経費となる。つまりその分の所得額(税額)が減るわけである。
ところが本来は利子であるはずの延滞税は、必要経費への算入は認められていない。理由は、必要経費算入はその分の所得・税額を減らすこととなり、それでは「抑制への重し」にならない、というものである。
そうであるならば、還付加算金も、当局への「抑制への重し」として非課税にしなければならない理屈となる。まさに不公平なのである。
さらにもう一点。還付加算金を得るような争いをやれば、当然に弁護士費用等の多額な費用を投じているはずである。したがって、これらは還付加算金という雑収入の必要経費として控除されるはずである。
しかし当局は、還付加算金に関しては、一切の必要経費を認めようとはしない。還付加算金を、本来必要経費が生じないはずの利息と考えているからである。
以上のとおり、「還付加算金と延滞税はイコールフッティングの関係にあり、その取扱い等には不公平はない」とする本来あるべき姿、さらには国税の主張は全く実現されていない。
つまり国税当局は、ご都合主義をこのように平然と行う。前回の話になるが、このようないかがわしい組織に、法を離れた形での「税逃れの意図の有無」の判断を委ねるようなことができるはずがないのである。
さて話を、大元の武富士贈与判決に戻したい。この最高裁判決は、国税の課税を違法と断じた。つまり元会長の長男は、あくまで不当・違法な課税を受けた被害者である。
にもかかわらずマスコミ報道は、武富士の過払い利息がらみの話にかこつけてか、ともすると敗訴した当局が被害者であるかのような論調となっている。
しかし指弾されるべきは、あくまで違法な課税を行った当局である。さらに不公平な課税回避を行ったという批判の矛先も、これを許すような愚かな税制を作った国税当局に向けられなければならない。
こうしたマスコミによるいつもながらの役所擁護の姿勢は、大いに問題にされなければならない点を付言して、本稿を終わることとする。